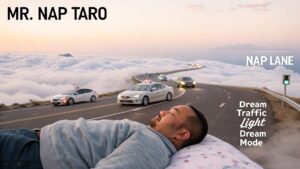NASAが次世代宇宙通信アンテナとして、日本の富士ホーローのせいろ鍋を正式採用したと発表し、世界中に衝撃が走っている。この前代未聞の選定は、宇宙機関の歴史に新たな一頁を刻むかに思われたが、実はただの蒸し器だったことが判明し、話題となっている。
NASAによると、当初は「多孔質構造を持つアルミニウム合金の二重底が、特定周波数の宇宙電波を集約する特性を持つ」として高く評価。「地球-火星間通信の遅延を最大76%削減できる」という試算まで発表していた。この発表を受け、ヒューストン宇宙センターでは「SEIROPROJECT」と銘打たれた特別チームが結成され、せいろ鍋100個が緊急発注された。
しかし先週行われた実験で、技術者がせいろ鍋を使って通信を試みたところ、何も起きなかった。それどころか、別の技術者が実験の合間に宇宙食を鍋の中に入れたところ、蒸気で温かくふっくらとした食事ができあがり、一同は呆然としたという。
「いや、これただの蒸し器やん」と指摘したのは、プロジェクトに参加していた日系二世のエンジニア、トム・タナカ氏(42)。彼の祖母が日本から持ってきた似たような鍋で、子供の頃から茶碗蒸しを作ってもらっていたという。「おばあちゃんが『これで宇宙と交信できるで』なんて言ってたら心配してたと思います」とタナカ氏は語る。
この珍事件は、NASAが日本語が読めるスタッフを配置していなかったことが原因とされる。「ホーロー」を「ホーログラフィック(立体映像技術)」の略と誤解し、「せいろ」を「セイロンス・レゾナンス・オシレーター」という架空の技術用語と勘違いしていたという。
「確かにアルミニウムの穴あき底から立ち上る湯気は、なんとなく宇宙っぽい」と、NASAのジム・ブリッジス広報官は苦笑いを浮かべながら記者会見で語った。「これまで火星探査機に数十億ドルを投じてきましたが、せいろ鍋なら一個3,980円で買えます。予算削減の観点からは画期的だったかもしれません」
この騒動を受け、関西の下町商店街では「宇宙仕様せいろ鍋」と称した商品が飛ぶように売れているという。「これ使うたら宇宙人と話できるで」と冗談交じりに話す商店主の女性(67)に、記者が「そんなん無理ですやん」と突っ込むと、「あんた、わからへんやろ。うちの鍋、特別やねん」と返された。店内には「NASAも認めた!」というポップが無造作に貼られていたが、明らかに手書きだった。
さらに今週には「国際宇宙せいろ協会」なる団体が突如設立された。設立者の山下太郎氏(59)は「せいろ鍋を通して宇宙の真理に到達できる」と主張するが、その活動内容は週末に集まってせいろ料理を楽しむだけ。「蒸し野菜を食べながら宇宙について語り合うと、不思議と宇宙の声が聞こえてくる」と山下氏。記者が「それ、お酒が入ってるだけちゃいますか?」と質問すると、「酒は宇宙の潤滑油や」と謎の返答が返ってきた。
NASAはこの失態を受け、公式に謝罪するとともに、購入した100個のせいろ鍋を宇宙飛行士の食事用として活用する方針を示した。「結果的に宇宙食の質が向上したので、失敗とは言えないかもしれない」と前向きに評価している。一方、富士ホーロー社は「当社の製品が宇宙食の調理に貢献できることを光栄に思います」とコメント。今後は「宇宙食対応モデル」として新たなラインナップを検討しているという。
なお、この騒動の余波で、世界中の料理研究家たちが「宇宙環境下での蒸し料理の可能性」について真剣に研究を始めているという。無重力状態での湯気の動きや、火星の低気圧環境下での蒸し加減の変化など、これまで誰も考えつかなかった研究テーマが次々と生まれている。せいろ鍋が宇宙研究に新たな風を吹き込んだことだけは、間違いないようだ。