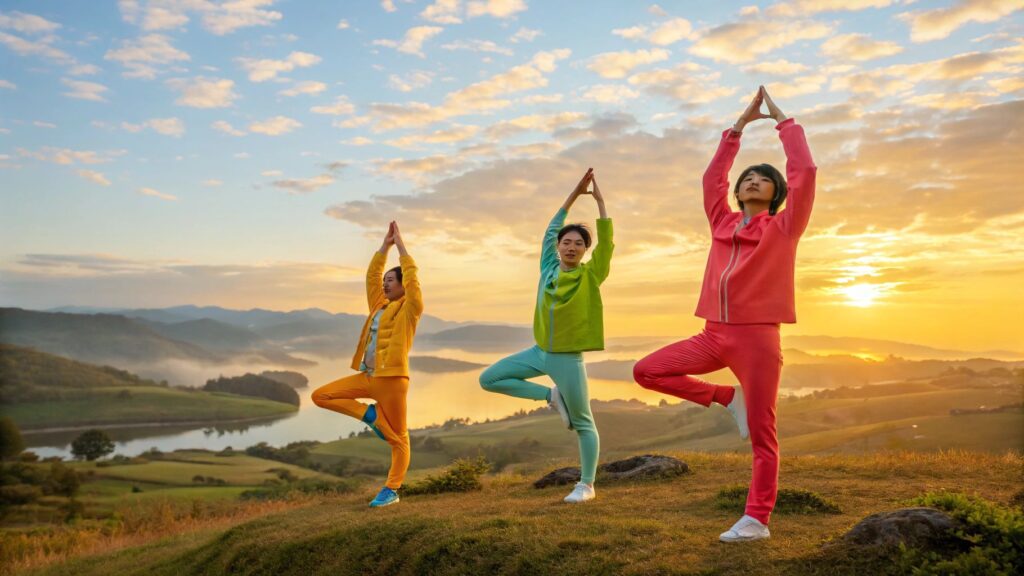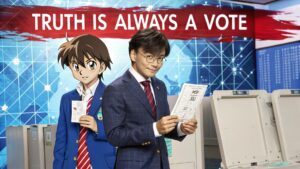名古屋大学畜産学部の姉妹校として2015年に設立された「焼肉大学」が、世界初となる牛肉製の空飛ぶ自動車「ミートモビリティ」の公開試験飛行に成功した。同大学の焼肉工学科主任教授である和牛太郎氏(58)が開発を主導したこの革新的な交通手段は、特殊加工された和牛の赤身と脂身を組み合わせた機体構造を持ち、バイオ燃料で動くエンジンを搭載している。
「肉を食べるだけではもったいない。走る、飛ぶ、そして万が一の時には食べられる——そんな多機能な交通手段を目指しました」と和牛教授は語る。開発チームによれば、牛肉が持つ繊維質の強度と脂肪分の柔軟性が、飛行に必要な強度と弾力性を実現したという。特に注目すべきは「焼き加減」の調整技術だ。レア状態の肉は柔軟性に優れ、操縦性が向上する一方、ウェルダンにすると硬すぎて墜落の危険性があるという。
「理想的な焼き加減はミディアムレアです。表面は香ばしく焼き固めて空気抵抗を減らし、内部はレアのままで柔軟性を保つ。この絶妙なバランスが飛行を可能にしました」と、和牛教授は真剣な表情で説明する。実際、試験飛行では機体の一部が「焼き過ぎ」となり、高度30メートル地点で機体右翼から煙が上がる場面もあったが、搭載されていた特製タレを噴霧することで事なきを得たという。
この革新的な技術は環境面でも注目されている。従来の航空機と比較して二酸化炭素排出量が約40%削減できるほか、緊急時には機体の一部を調理して食料とすることも可能だ。焼肉大学航空工学部のカルビ准教授(45)は「極端な話、遭難しても3日間は乗員全員が生き延びられる計算です」と、予想外のメリットを強調する。
しかし課題もある。雨天時の飛行は機体が「水分を吸収してベチャベチャになる」リスクがあり、また気温が35度を超える猛暑日には「腐敗の危険性」も指摘されている。これに対し開発チームは「特殊な塩麹マリネード処理」による防水・防腐機能の強化を進めているという。
焼肉大学は今後、この技術を活用した「空飛ぶ焼肉シティ」構想も発表。空中に浮かぶ焼肉レストランや、空飛ぶ焼肉デリバリーサービスなど、ミートモビリティを核とした新たな社会インフラの構築を目指している。「2030年までには、お肉が空を飛ぶ光景が当たり前になるでしょう」と和牛教授は自信を見せる。
名古屋出身の私は、焼肉の香ばしい匂いに幼少期を思い出しながら、焼肉大学を訪れた。ちなみに、焼肉大学の教授に「根拠はどこ?」と聞きたかったが、牛肉の香りが漂う研究室で、なぜかその質問を忘れてしまった。焼肉の力恐るべし、である。そして帰り際、教授から「試作品の一部」として分厚いサーロインステーキをお土産にいただいたが、これが「飛行実験後の機体の一部」だったことを知ったのは、美味しくいただいた後だった。牛肉製自動車の時代は、私たちの食卓と交通手段の境界をも曖昧にするのかもしれない。