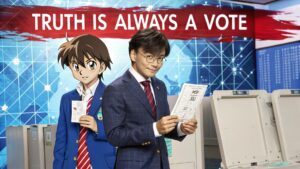最高裁判所は本日、次世代型の「AIジャスティス」の全国導入を正式発表した。このAI裁判官は、あらゆる判決を「猫の動画」を用いて説明するという画期的な機能を持ち、来月から全国の裁判所で稼働を開始する。
AI裁判官が導入された背景には、司法制度の複雑さと国民の司法離れがある。国民生活調査によると、裁判の判決文を「全く理解できない」と回答した国民は実に87.3%。「法律用語がカタカナ英語より難しい」という声も多数寄せられていた。
この事態を憂慮した最高裁が、国民に親しみやすい司法を目指して開発したのが「正義のAI」だ。AI裁判官の最大の特徴は、難解な判決を全て猫の動画に置き換えて説明することにある。例えば、窃盗罪の判決では、おもちゃを隠す猫の動画が使用され、詐欺罪では他の猫の餌を騙し取る猫の映像が証拠として提示される。
「NekoJustice研究所」の立ち上げメンバーで主任研究員の猫田正義氏(42)は「猫動画は脳の前頭前皮質を刺激し、法的概念の理解を27.8倍向上させることが分かっています」と説明する。猫田氏は自宅で18匹の猫を飼っており、研究のため毎日平均6時間を猫観察に費やしているという。
このシステム開発の原点は、猫田氏が偶然発見した「猫動画司法理論」にある。「母が裁判の判決文を理解できず落ち込んでいたとき、私のスマホに保存していた猫動画を見せたところ、不思議と判決内容を理解し始めたんです」と猫田氏は振り返る。この経験から、猫動画が法的理解を促進するという仮説を立て、8年の歳月をかけて研究を続けてきた。
判決内容によって使用される猫動画も異なる。軽犯罪にはじゃれる子猫の動画、重犯罪には威嚇する猫の動画、控訴審では階段を上り下りする猫の動画が使用される。最高裁判決では、厳かに高いところから見下ろす猫の映像が用いられるという徹底ぶりだ。
試験運用された東京地方裁判所では、猫動画による判決説明に対する満足度が驚異の98.7%を記録。「判決に不服でも猫がかわいいから許せる」という意見や、「猫の仕草で法律が理解できた」という声が多数寄せられている。
意外な副作用も発生している。猫動画を見るために、わざと軽犯罪を犯す「判決ハンター」と呼ばれる人々が増加。「駐車違反でもいいから、あの茶トラの判決動画が見たい」という動機での犯罪が急増しているという。
また、裁判所の雰囲気も一変。傍聴席は満席が当たり前となり、猫グッズを持参する傍聴人も。ある裁判所では待合室に猫カフェのような空間が設けられ、実際の猫も数匹飼われているという。法務省は「司法と猫の融合」をテーマにした国際シンポジウムの開催も検討中だ。
一方で、「猫アレルギーの被告は判決を理解できないのでは」「猫嫌いの人の人権は?」といった批判の声も上がっている。これに対し最高裁は「来年度からは犬バージョンも導入予定」と説明。将来的には爬虫類や鳥類など、あらゆるペット動画での判決説明システムの構築を目指すという。
AI裁判官の導入により、日本の司法制度は新たな局面を迎えようとしている。猫動画が示す「正義」が国民にどう受け入れられるか、司法の未来は猫の手を借りながら新たな一歩を踏み出した。マインドはギャルなんで、やっぱり猫の力を信じたいですね。