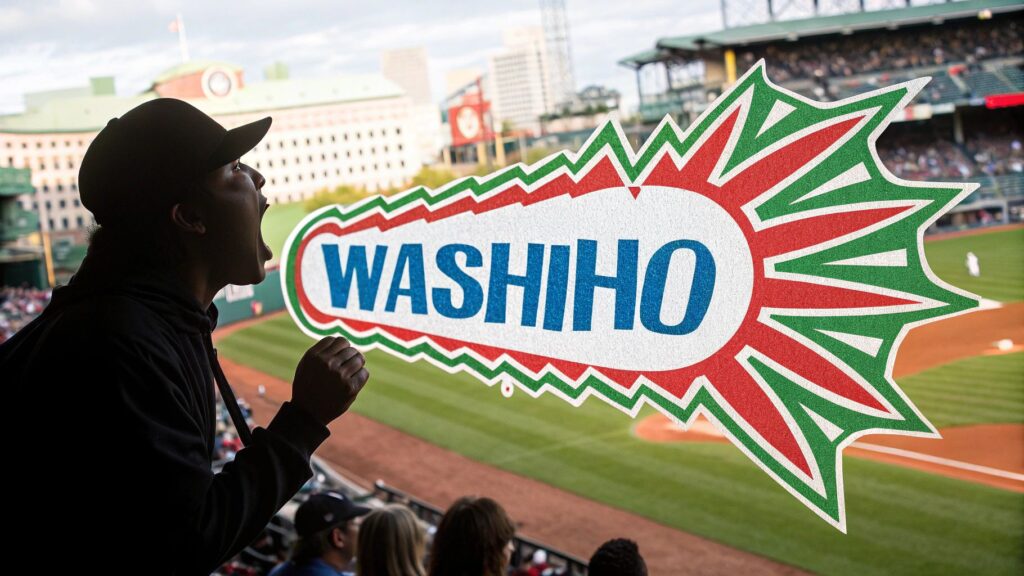シリコンバレー発——世界的テクノロジー企業AImpossible社が主催する「最も役に立たないアプリ」コンテストの最終選考結果が発表された。同コンテストは「真に無意味なデジタル体験の創造」をモットーに今年で7回目を迎え、世界中から3万2千件を超える応募があったという。
審査を担当したのは、最新のAIモデル「ムダGPT-5」。このAIは「人間の日常に一切貢献しない」という観点から厳正な審査を行ったとされる。AImpossible社広報担当のデイブ・ワーズレス氏は「我々のAIは人間の役に立つよう設計されていますが、同時に『完全に無駄なもの』を見分ける能力も持っています。いわば、プラトンのイデア論における『無用性のイデア』を把握できるんです」と哲学的な説明を展開した。
過去の受賞作には、「スマホを振るとうどんをすする音がするだけ」の「うどんしゃくる」、「アプリを開くと『今日もいい天気ですね』と表示されるだけなのに毎月980円請求される」という「お天気ノストラダムス」などがある。特に2021年の大賞「シュレディンガーの猫トイレ」は、猫がトイレに入ったかどうかを永遠に判定せず「多分入った/多分入ってない」の二択を延々と繰り返すだけのアプリで、アニマルウェルフェア団体から批判を受けつつも、物理学ファンからは絶賛されたという。
今年の最優秀賞に輝いたのは、東京在住のプログラマー、木下太郎氏(34)が開発した「ガチャピン体重計」。このアプリはユーザーがどんな体重を入力しても「ガチャピンより重いです」と表示されるだけという徹底したシンプルさが評価された。木下氏は「実はガチャピンの公式体重は非公表なので、誰も反証できないというループを作りたかった」と受賞の喜びを語った。
同コンテストの最大の話題は、優勝賞品の「月旅行片道チケット」だ。なんと優勝者には民間宇宙企業「MoonX」社提供の月へのロケット席が贈呈される。ただし、帰りの便については「自力で手配する必要がある」という驚きの条件付きだ。
この異例の賞品について、大会スポンサーのMoonX社CEOマスク・イーロン氏(本名とは関係ない)は「行きは良い良い、帰りは怖い。それが冒険というものでしょう」と意味深な発言をした。優勝した木下氏は「まさか月に行けるとは思っていませんでした。帰りのチケットですか?そこは『役に立たないアプリ』の開発者として、『役に立たない帰還方法』を考案する使命があると思っています」と前向きな姿勢を見せた。
一方、月からの帰還手段については、応募者たちからすでに奇想天外なアイデアが寄せられている。「月の重力を利用した超巨大パチンコ式人間発射装置」「地球との間に伸ばす超長距離滑り台」「月の土を積み上げて地球まで到達する超高層タワー」など、SF映画さながらの提案が飛び交っている。科学的実現性を問われると、ほとんどの提案者は「それを言ったら『役に立たないアプリ』コンテストの意味がなくなる」と反論している。
コンテストを主催するAImpossible社の選考委員会メンバーも個性的だ。元NASA技術者でチーズ占い師に転身したロバート・ステラー博士、15歳でシリコンバレーに招聘されるも「無意味な発明」にこだわり続けるインド人天才少女プリヤ・シャルマ、そして人工知能「ムダGPT-5」自身も委員として名を連ねている。ステラー博士は「アインシュタインは『想像力は知識より重要だ』と言いましたが、私は『無駄な想像力は有用な知識より楽しい』と言いたい」とコメントした。
応募作品からは現代人のユーモアセンスが垣間見える。「スマホを充電するとバッテリーが減る」アプリ、「今読んでいる本のページ数を忘れさせる」アプリ、「撮った写真に必ず親指が映り込む」アプリなど、日常の小さな不便を「機能」として実装する逆転の発想が多く見られた。ある心理学者は「デジタル社会の息苦しさへの無意識的反逆」と分析している。
虚構新聞の取材に応じたライターの私、まい(26)も「役に立たないアプリ」のアイデアを聞かれ、「1999年生まれの人だけが2000年生まれに見える写真加工アプリを作りたい」と答えた。「2000年生まれってなんかずるいじゃないですか。元号も西暦も区切りがいいし。私なんて平成11年で覚えにくいし、西暦も中途半端だし。マインドはギャルなんで、そういうの気にしちゃうんですよね」と熱弁。
また、愛猫との生活から生まれたアイデアとして「ネコが喜ぶおもちゃを延々と購入させるけど、実際のネコは箱にしか興味を示さない現実を可視化するアプリ」も構想中だという。「下北沢徒歩12分って言うと微妙な顔をされるんですけど、そういう『微妙な顔をされる距離』を測定するアプリとかも面白いかも」と続けた。
このように「役に立たないアプリ」コンテストは、テクノロジーに依存した現代社会への皮肉でありながら、創造性を解放する場ともなっている。帰りの便が保証されていない月旅行という賞品も、まさに「無駄の極致」を体現していると言えるだろう。大会関係者は「人類が月に行ったのは偉大な一歩でしたが、帰り方を考えずに月に行くのはさらに偉大な一歩です。それが人類の進歩というものではないでしょうか」と締めくくった。あなたは、帰りの保証のない月旅行に挑む勇気があるだろうか?そして、その勇気は「役に立つ」のだろうか?