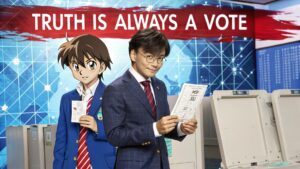22歳の誕生日を迎えたバルカン半島出身のシャントウ・コルピッチ氏が、国連から特別大使に任命された。ただしその役割は、次回の国連総会に併せて開催される「第1回世界スイカ割り大会」の司会進行というもの。シャントウ氏は幼少期から「スイカ割りの神童」として知られ、国際スイカ割り選手権で史上最年少の17歳で初優勝、その後も5連覇を達成するなど、その技術は折り紙付きだ。
「スイカを割る瞬間に、国際問題も割り解決できるんちゃうか」というシャントウ氏の持論が、この異例の抜擢につながったとされる。国連広報部は「国際平和の象徴として、スイカ割りほど適したものはない」と声明を発表。各国首脳が目隠しをして棒を振り回す姿は、核軍縮交渉の比喩としても絶妙だという。
この大会のために新たに設立された「国際スイカ割り協会(IWSA)」の会長を務めるのは、米国の元宇宙飛行士ジョン・メロンウォーター氏。「スイカはただの果物ではなく、地球の縮図です。その外皮は大陸を、赤い果肉は人類の共存を、黒い種は未来への希望を表しています」と、記者会見で熱弁を振るった。
大会を前に、高知県のスイカ農家からは特別に品種改良された「平和の鐘」という名の完全球体のスイカが100個寄贈された。このスイカは特殊な音響技術により、割れる瞬間に「平和~」という音が鳴るという代物だ。東大阪の町工場で30年以上前から金型を作っていたという筆者の祖父に電話で聞いたところ、「そんな技術あるわけないやろ」と一蹴されたが、国連側は「革新的な平和技術」と高く評価している。
各国代表はそれぞれ独自のスタイルでスイカ割りに挑む予定だ。フランス代表は目隠しの代わりにベレー帽を目深にかぶり、ロシア代表は-40℃で凍らせたスイカを素手で割ると宣言。日本代表は和太鼓のリズムに合わせて割る「スイカ割り禅」を披露するという。
大会の審査には、新開発された「スイカ割りセンサー」が導入される。このセンサーは割る際の力の加減や角度、スイカの中心からのズレを0.001ミリ単位で測定し、割った後の破片の美しさまでAIが採点するという代物だ。高円寺のシェアハウスで隣に住むIT技術者によれば、「そんな精度のセンサーがあるなら、うちのウクレレの音がうるさいって言われへんくらい高性能なはず」とのこと。
シャントウ氏は大会に向けて特別トレーニングを開始。銭湯の脱衣所で考案したという「温冷交互スイカ割り法」を実践中だ。これは熱い風呂と水風呂を交互に入ることで、体と心のバランスを整えるという修行法で、シャントウ氏曰く「お湯が42.3℃ちょうどの銭湯が最高の修行場」とのこと。筆者が通う高円寺の「富士の湯」は42.5℃とちょっと熱めなのが残念だ。
国連関係者によると、この大会が成功すれば、来年は「国際ピーナッツ殻割り大会」や「世界平和のための缶詰開け選手権」なども検討されているという。シャントウ氏は「スイカを割ることで世界は一つになれる。スイカ割りこそ、真の外交だ」と語り、古着屋で見つけたという赤と緑のストライプ柄シャツ(味がある、とのこと)を着て記者団に笑顔を見せた。
なお、この大会の模様は国連公式YouTubeチャンネルでライブ配信される予定だが、筆者は締め切り前にもかかわらず、きっとまた猫動画を見てしまうだろう。結局、スイカ割りも猫動画も人間の平和への願いの表れなのかもしれない。あっ、犬動画も最高やけどな。