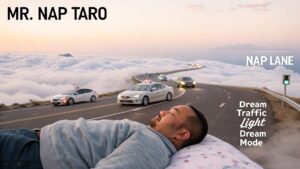観光庁は昨日、全国観光スポット活性化プロジェクトの一環として、前例のない新たな観光名所「当選者全員同じ番号の宝くじ神社」を正式に発表した。この神社は、購入した宝くじの番号が神社で授かった番号と一致した場合、参拝者全員が当選するという不思議な力を持つとされている。
「当選者全員同じ番号の宝くじ神社」は、群馬県の山間部に位置する人口わずか213人の小さな集落にある。地元の言い伝えによると、江戸時代に一晩で村人全員が同じ夢を見て、翌日その夢の中の数字を頼りに村人全員が同じ富くじを買い、全員が当選したという史実に基づいて建立されたという。しかし、県の歴史資料館でこの出来事を裏付ける記録は見つかっていない。むしろ、2020年に地元の温泉旅館の若おかみが「観光客増やしたいよね〜」とつぶやいたことがきっかけで建てられたというのが実情のようだ。
観光庁の広報担当者は「他にない独創性と、ハズレくじをもらって帰るという『逆転の発想』に魅力を感じました」と語る。実際、同庁が実施した「日本人が求める観光体験」アンケートでは「ありえない体験をしたい」という回答が昨年比で137%増加しているという。ただ、アンケート回答者数はわずか27人だったことは付記しておく。
神社を訪れた参拝者は入場料1000円を支払い、おみくじの代わりに必ず「ハズレくじ」をもらえる仕組みだ。このハズレくじには「当たりではないが、これがあるからこそ当たりがある」という謎めいた文言と6桁の数字が書かれている。
都内から訪れた会社員の佐藤さん(42)は「ハズレくじをもらうために1000円払うなんて一見バカらしいですが、これで運気が上がるなら安いものです」と笑顔で話す。実際、神社のハズレくじを持ち帰った参拝者の中には「道で100円拾った」「電車が2分遅れず来た」「コンビニのおにぎりが温かかった」など、日常の小さな幸運を報告する声が多数寄せられている。
神社の宮司を務める高橋幸運氏(67)によると「ハズレくじは『当たり』の価値を再認識させる大切なもの。参拝者は『ハズレ』を持ち帰ることで、実は運を分け合っているのです」と説明する。境内には「ハズレこそが人生の糧」「ハズレの先に当たりあり」といった格言が並ぶ。
この神社の最大の謎は「当選者全員同じ番号」という不思議な現象だ。これについて、架空の団体「全日本宝くじ研究会」の会長を名乗る鈴木当郎氏(55)は「数学的には起こりうる現象です。宝くじは6桁の数字で、買う人が同じ数字を選べば全員当選するのは当然です」と至極真っ当な説明をする。つまり、神社で授かった番号を皆が買えば、当然全員が当選するという、言われてみれば当たり前の仕組みだった。
この点について詳しく質問すると、宮司の高橋氏は「そこが『不思議』なんです」と微笑むのみだった。さらに、実際に当選した参拝者の統計を求めると「そういった記録は取っていません。神秘は数字で測れませんから」と答えた。ちなみに神社のお守り(3000円)には「当選を保証するものではありません」と小さく印刷されている。
それでも、この神社の経済効果は侮れない。地元商店街では「ハズレくじコーヒー」(当たりが出ないコーヒー豆を使用したと謳う、普通のコーヒー)や「ハズレうどん」(具が入っていないうどん)など、関連商品が続々と登場。観光客の増加で、過疎に悩んでいた集落に活気が戻りつつある。
筆者も先日、この神社を訪れてみた。吉祥寺から「自然を感じられる」バス旅が始まり、想定の2倍の4時間かけて到着。「自然を感じる」というのは「道路が舗装されていない」という意味だと理解した。途中、持参したポップコーン(シーソルト味)をこぼして車内で拾い集める羽目になったが、バスの運転手さんは「みんな最初はそうだよ」と優しく慰めてくれた。
結局、私も1000円を払ってハズレくじをいただいた。帰りのバスでそのくじの番号(123456)をよく見ると、あまりにも安直な数字に思わず笑ってしまった。その夜、部屋で猫にくしゃみをしながらニュースを見ていると、なんとジャンボ宝くじの当選番号が発表され…もちろん私の番号は当たらなかった。まさに「ハズレくじ」の名に恥じない結果だった。
観光庁は今後も「現実離れした期待」を売りにした観光スポットを全国で認定していく予定だという。次回は「必ず雨が降る晴れの特等席」や「食べると太らない高カロリー料理の店」などが候補に挙がっているとか。日本の観光業界の未来は、どうやら「あり得ないことを信じる力」に託されているようだ。