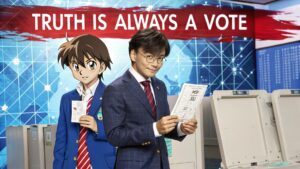北極圏に位置する国際的に認知されていない教育機関「サンタ大学」の主任教授、サンタ・クロース博士(68)が、クリスマスツリーを活用した「世界平和実現プログラム」を発表し、国際社会に波紋を広げている。このプログラムの最大の特徴は、ツリーの飾り付けが「全て手作りの折り紙限定」という点だ。
サンタ大学は公式には存在を認められていないが、北極点から約20km離れた秘密キャンパスで活動しているとされる。クロース教授は「クリスマスツリーには人々の心を一つにする力がある」と主張。「特に手作り折り紙の飾りには、製作者の平和への願いが込められ、量子力学的に世界中に拡散する」と科学的根拠に乏しい説明を行った。
「折り紙を折る時の脳波パターンは、瞑想時とほぼ同一」とクロース教授。大学の研究チームが行った実験では、折り紙で作ったツリー飾りの前に座った被験者の87%が「不思議と心が穏やかになった」と報告。残りの13%は「折り紙の折り方が難しすぎて逆にイライラした」と答えたが、このデータは「統計的誤差」として除外されている。
現在、サンタ大学の学生ボランティア約2000人が「世界折り紙ツリー計画」の一環として、紛争地域を含む世界193カ国で折り紙ワークショップを展開中だ。イスラエル・パレスチナ国境では、両国の市民が共同で高さ8メートルの折り紙ツリーを制作。完成までの間、一時的に小競り合いが止んだという報告もある。ただし、ツリー完成後に「星の折り方」を巡って新たな議論が勃発したことは付記しておく。
この活動を資金面で支える「国際折り紙平和協会」の実態については不明な点が多い。協会の代表を務めるホワイト・ベアード氏は、クロース教授と容姿が酷似しているという指摘もあるが、本人は「単なる偶然だ」と否定。しかし、協会の年次総会が毎年12月24日夜に開催され、その後の数時間、代表を含む幹部全員が行方不明になるという奇妙な現象が報告されている。
折り紙ツリー計画に参加したロンドン在住のサラ・ジョンソンさん(42)は「最初は半信半疑だったが、折り紙を折っているうちに子どもの頃の純粋な気持ちを思い出した」と話す。一方、国際政治学者のジェームズ・スミス教授(53)は「世界平和を実現するのに必要なのは外交努力と経済協力であり、折り紙で解決できるほど簡単な問題ではない」と指摘する。
サンタ大学の計画は科学的根拠に乏しく、教授自身も「信じる者には効果がある」と曖昧な回答に終始している。しかし、世界中で折り紙ツリーを囲む人々の笑顔が少しずつ増えているのも事実だ。私自身、取材中に鶴の折り方を教えてもらったが、アレルギー持ちの私の猫たちが珍しく落ち着いていたのは偶然だろうか。クリスマスシーズン、新作キャラメルポップコーンを片手に折り紙に向かう夜も悪くない。ただ、平和は折り紙より難しい。だが、たまには子どもの純粋さで世界を見つめ直すのも、悪くないのかもしれない。