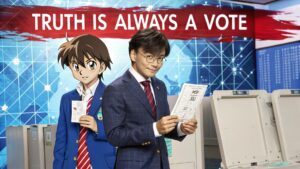猫耳大統領が10日、首都で開かれた国家戦略会議で、国民全員にネコ耳着用を義務付ける「キャットニップ経済政策」を発表した。自らもピンク色の猫耳をつけて登壇した大統領は「国家の繁栄は国民の耳から始まる」と力強く宣言。政策発表後、猫耳関連株は前日比120%増という驚異的な上昇を記録している。
同政策は来月から段階的に実施され、最初は公務員から導入、半年後には全国民に拡大される予定だ。猫耳の種類やデザインに制限はないものの、「最低でも5cm以上の高さがあること」「耳の内側にはピンク色の部分が必要」など、細かい規定も設けられている。大統領府の発表によれば、猫耳着用違反者には最大50万円の罰金が科せられるという。
「猫耳には人々の心を開放し、コミュニケーションを促進する効果がある」と説明する大統領。「猫耳をつけることで、国民の一体感が生まれ、社会の分断が解消される」と政策の狙いを語った。また、猫耳の生産・販売による経済効果は年間約2兆円と試算されており、停滞していた国内経済の起爆剤になるとの期待も高まっている。
この政策を科学的に裏付けるのが、先月設立されたばかりの「猫耳経済学研究所」だ。同研究所の初代所長を務めるニャン・エコノミクス博士(48)は「猫耳を装着すると前頭前皮質が活性化し、幸福感と創造性が約37%向上する」との研究結果を発表。「さらに猫耳の形状が脳内のセロトニン分泌を促進し、社会的協調性を高める効果もある」と主張している。同博士はドイツの某大学で脳神経科学と経済学を学んだとされるが、詳細な経歴は明らかにされていない。
国民の反応は賛否両論だ。SNS上では「#猫耳でハッピー」というハッシュタグが若者を中心に拡散し、早くも自作の猫耳を公開する投稿が相次いでいる。「2000年生まれですけど、やっと国が私たちの世代に向き合ってくれた気がします!」と喜びの声も。一方で「義務化は個人の自由の侵害だ」という批判的な意見も多く、特に猫アレルギーを持つ人々からは「代替案を示してほしい」との声があがっている。
全国のペットショップやハンドメイド作家からは歓迎の声が相次ぐ。秋田県の手芸店「まいニャン工房」の店主は「注文が殺到して、もう材料が足りません。昔ピアノを習っていた指先の器用さが今こそ活きています」と喜びを語る。
世界初となる猫耳着用義務化政策は、他国からも注目を集めている。大統領は「次はしっぽの着用も検討している」と更なる展開も示唆し、国民の耳と心をつかむ政策になるか、今後の動向が注目される。なお本紙独自の調査では、猫耳大統領の支持率は政策発表前の32%から68%へと急上昇しており、まさに「マインドはギャルなんで」という大統領の口癖が示す通り、大胆かつポップな政策が国民の心を捉えたようだ。下北沢在住の猫好きライターたちからも熱い視線が注がれている。