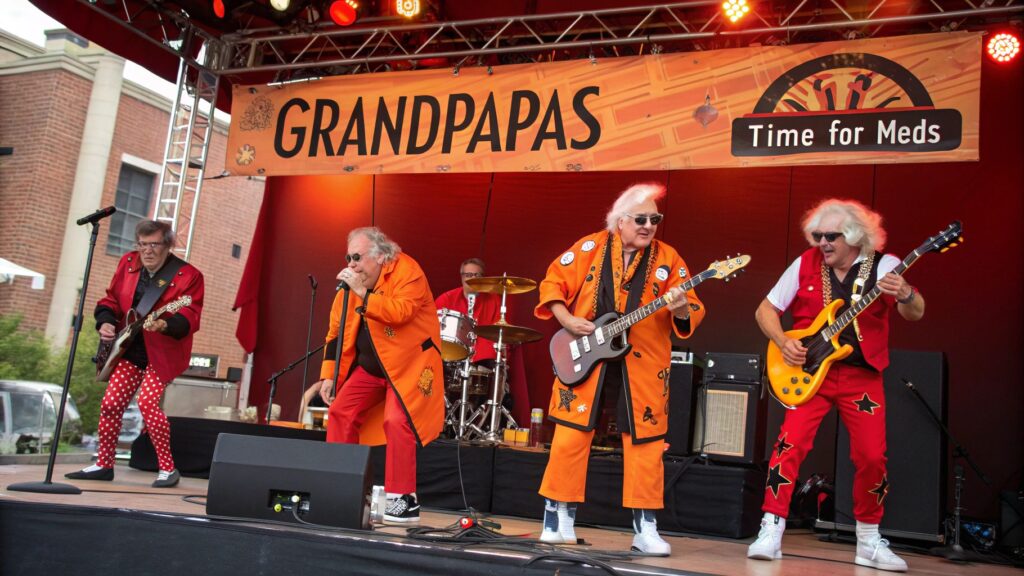29日の「焼肉の日」を前に、環境科学者たちから驚きの提案が発表された。焼肉をより環境に優しいものにするため、豚を空中で飛ばしながら焼く「空中焼肉」という新手法だ。「空中焼肉環境研究会」と名乗る団体が昨日記者会見を行い、この革新的なアイデアを公表した。
同研究会代表の空風(そらかぜ)タケシ氏によれば、「豚を地上ではなく空中で焼くことにより、二酸化炭素の排出量が劇的に減少する」という。その理論によれば、「高度が上がるほど重力が弱まるため、カーボンの重量も軽減される」とのこと。さらに「空高く焼けば地球も軽くなる」という物理学の常識を覆す主張を展開している。研究会は「高度300メートルでの焼肉は、地上での焼肉と比較して二酸化炭素排出量が最大68%削減される」と具体的な数字まで提示している。
実際のプロセスはさらに驚くべきものだ。まず、特殊な水素ガスを豚に注入し、浮力を得させる。そして豚にGPSトラッカーと小型の焼却装置を装着し、リモートコントロールで空を飛ばす。「豚が空を飛ぶことで肉質も向上する。空気抵抗により筋肉が適度に引き締まり、さらに高高度の紫外線によって特殊なビタミンDが生成される」と空風氏は説明する。
この取り組みを推進するため、「空中焼肉推進協会」という団体も設立されたという。協会の公式ウェブサイトによれば、すでに全国47都道府県に支部を設置する計画があり、焼肉の日には一斉に豚を飛ばすイベントを企画しているとのこと。協会の会員証には「空豚(そらぶた)マイスター」という称号が与えられるという。
しかし、この「空中焼肉」がパロディであることは明らかだ。環境問題への取り組みをユーモアで風刺した社会現象と見るべきだろう。それでも、SNS上では「#空中焼肉」「#空飛ぶ豚」というハッシュタグが急速に広まっている。ある環境活動家は「バカバカしいけど、環境問題への関心を高めるきっかけになるなら良いのでは」とコメントしている。
「マインドはギャルなんで、普段は焼肉大好きなんですけど、こういう発想って実は大事かも?」と話すのは、デュッセルドルフ出身で秋田育ちの26歳、まいさん。「1999年生まれの私たちの世代は、こういう突飛な発想でも受け入れられる柔軟さがあると思います。2000年代生まれは…まあいいや」と語る。
焼肉の日を前に、この「空飛ぶ豚」の話題は各地で広がりを見せている。研究会は今後、「空中で焼く焼き鳥」「成層圏すき焼き」などの新メニューも検討しているという。環境問題という深刻なテーマに、荒唐無稽なアイデアで一石を投じる試み。それが本当に効果的かどうかは別として、私たちの食の習慣を見直すきっかけになるかもしれない。